児童扶養手当は実家暮らしでもらえます!
ただし、もらえる金額は自分の所得とあわせて同居する両親の所得が大きく関係してきます。
現在、実家暮らしをするひとり親家庭は全体の50%ほどになっています。
実家に戻っても変わらず児童扶養手当はもらえるものだと思っていざ暮らし始めたら、児童扶養手当がまさかの支給停止!
そんなことも少なくないのが事実です。
この記事では、「児童扶養手当がどうやったら支給停止になるのか?」を詳しく説明していきますよ!
最後までぜひご覧いただき、停止されることがないようにお役立ていただければ幸いです。
児童扶養手当は実家暮らしでも受給できる?支給額はいくらになる?
児童扶養手当額は自身の所得によって決まってきます。
しかし、実家暮らしともなれば自分の所得だけではなく同居する家族の所得も児童扶養手当額を決める審査の対象となるのです。
それでは、児童扶養手当額がどのように決まるのかみていきましょう。
児童扶養手当の支給額について
児童扶養手当は自分が扶養する子どもが18歳に到達した年度の3月分まで支給されるものです。
(ただし、児童に一定の障害がある場合は、20歳未満まで延長されます)
①【令和5年度】児童扶養手当額(月あたり)
| 扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 |
| 1人目 | 44,140円 | 44,130円〜10,410円 |
| 2人目 | 10,420円 | 10,410円〜5,210円 |
| 3人目 | 6,250円 | 6,240円〜3,130円 |
「全部支給」になるか「一部支給」かになるかは自身の所得金額(=手取り額)によります。
自身の所得に対して、児童扶養手当が全部支給になるか一部支給かの判断は次のとおりです。
①【令和5年度】所得制限限度額について
父、母、養育者(孤児等の養育者は除く)の場合
| 扶養親族数 | 全部支給 | 一部支給 |
| 0人 | 49万円 (収入122万円未満) | 49万円以上192万円未満 (収入約122万円以上 311万円未満) |
| 1人 | 87万円 (収入160万円未満) | 87万円以上230万円未満 (収入約160万円以上 365万円未満) |
| 2人 | 125万円 (収入215万円未満) | 125万円以上268万円未満 (収入約215万円以上 412万円未満) |
| 3人 | 163万円 (収入270万円未満) | 163万円以上306万円未満 (収入約270万円以上 460万円未満) |
②受給者本人(シングルマザー)に扶養義務者がいる場合
| 扶養親族数 | 配偶者、扶養義務者 |
| 0人 | 236万円未満 (収入約372万円未満) |
| 1人 | 274万円未満 (収入約420万円未満) |
| 2人 | 312万円未満 (収入約467万円未満) |
| 3人 | 350万円 (収入約515万円未満) |

ところで、扶養義務者って何のことかな?
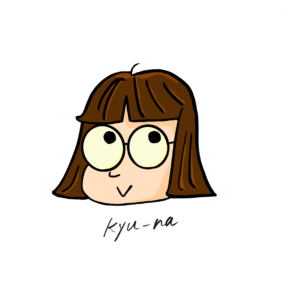
説明するよ!
簡単に言うと、同居している両親や生活費を共有している直系血族
(父母、祖父母、子など)のことを指すよ!

なるほど!
じゃあ実家で両親と一緒に暮らすと、両親が扶養義務者ってわけね。
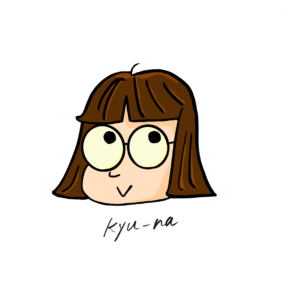
そうそう!
両親のどちらかが働いていたりすると、両親の所得額が重要になってくるの。
児童扶養手当対象外になったりするから、要注意ね!

対象外?!
どんな場合にそうなるのかしら。
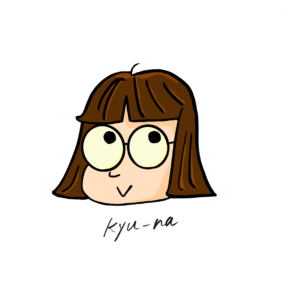
そうね!
次で具体例を2つあげてみるから、
いっしょにみていきましょう♪
シングルマザー(母親・子ども1人)と両親で暮らす場合
シングルマザー(母親・子ども1人)と両親で暮らす場合
シングルマザーのゆみさんは子ども1人と両親(父母)と暮らす4人世帯。
ゆみさんの給与所得は年間150万円。
実家の父親は65歳。まだ働いていて、給与所得が年間150万と年金所得が100万。(年間合計250万円の所得)
実家の母親は65歳。無職、父親の扶養に入っている。ただし、年金は受給中。(年間30万円の年金所得あり)
まとめると、
- ゆみさんの所得は年間150万円。
- ゆみさんのお父さんの所得は250万円。
- ゆみさんの母親はお父さんの扶養に入っている。年金所得が30万円。
まず、児童扶養手当の支給が全部支給か一部支給かを確認します。
「①【令和5年度】所得制限限度額について」の表を見てください。
ゆみさんは、「子どもが1人」で「年間所得が150万円」なので、所得が87万円以上230万円未満の範囲を見ます。
つまり、児童扶養手当は一部支給の対象ということがわかります。
続いて、同居の両親がいますので、扶養義務者の所得額で児童扶養手当の支給対象かどうかが決まります。見ていきましょう。
「②受給者本人(シングルマザー)に扶養義務者がいる場合」の表を見てください。
お父さんの所得は合計で250万。扶養はお母さん1人なので、扶養親族数1人の箇所を見ます。
所得が274万円未満の範囲ですから、児童扶養手当の受給が可能です。
ゆみさんの場合
両親と同居しても児童扶養手当(一部支給)の対象

つまり、
両親と同居でも児童扶養手当は支給対象なのね!
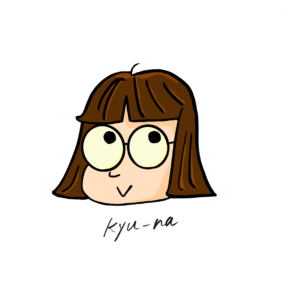
そうなの!
同居するだけで児童扶養手当が対象外になるわけじゃないのよ!

でも、所得のことが関係しているみたいだけど…
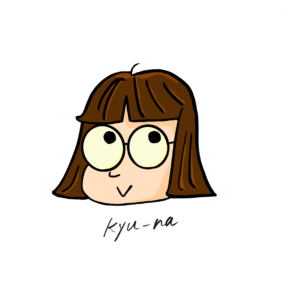
そうなの。
所得が増えれば児童扶養手当の支給額も変わってくるのよ。
次の例も見てみて!
シングルマザー(母親・子ども2人)と両親で暮らす場合
シングルマザー(母親・子ども2人)と両親で暮らす場合
シングルマザーの陽子さんは子ども2人と両親(父母)と暮らす5人世帯。
陽子さんの給与所得は年間150万円。
実家の父親は65歳。現在も働いていて、給与所得が年間210万と年金所得が150万。(年間合計360万円の所得)
実家の母親は65歳。パート勤務で年金も受給中(所得はパート勤務で年間60万円と年金30万円の合計90万円。)
まとめると、
- 陽子さんの所得は年間150万円。
- 陽子さんのお父さんの所得は年間360万円。
- 陽子さんの母親はパート所得と年金所得で年間90万円。
まず、児童扶養手当の支給が全部支給か一部支給かを確認します。
「①【令和5年度】所得制限限度額について」の表を見てください。
陽子さんは、「子どもが2人」で「年間所得が150万円」なので、所得が125万円以上268万円未満の範囲を見ます。
つまり、児童扶養手当は一部支給の対象ということがわかります。
続いて、同居の両親がいますので、扶養義務者の所得額で児童扶養手当の支給対象かどうかが決まります。見ていきましょう。
「②受給者本人(シングルマザー)に扶養義務者がいる場合」の表を見てください。
お父さんの所得は合計で360万。扶養はお母さん1人なので、扶養親族数1人の箇所を見ます。
所得360万円が274万円未満の範囲を超えているので、児童扶養手当の受給は対象外です。
児童扶養手当は実家暮らしでも受給できる?実家暮らしだと支給されにくい理由
実際の私の体験から言うと、正直実家暮らしだと「支給されにくい」です。
理由は2点あります。
同居人(両親等)に高額な所得がある。
自分の収入よりも実家の両親がまだ「現役バリ」の収入を得ている可能性が高いからです。
当時、役所の担当者に相談したらこう言われました。
住民票上は別世帯、生計も別だけど、一つ屋根の下で生活していれば実際に援助と言う形でお世話になることもあるから、そういった基準を設けているんです。
なるほど、公平な目線での判断なんでしょうね。
すべてのシングルマザーに戻ることができる実家があるとは限りませんからね。
残念に感じますが、仕方がないことです。
高額な養育費をもらっている。
シングルマザーが高額な養育費を受け取っている場合は要注意ですよ。
養育費の8割相当額は自分の所得に加算されます。
シングルマザーの給与収入があまりなくても、高額な養育費をもらうことで年間の所得額が増えます。
所得の合計額が増えれば、児童扶養手当額も変わってきます。
場合によっては、児童扶養手当支給の対象外となりますので気をつけてください。
実家暮らしで扶養手当どうなる?よくある質問Q&A
Q1:同居するかどうかを判断する「自分の所得額」の目安はいくらぐらいですか?
A1: 自分に子どもが1人の場合だと、自分の所得が230万円未満であれば児童扶養手当(一部支給)がもらえます。(2人の場合は268万円未満)
しかし、実家の父親(母親を扶養している)の所得が274万円以上になると、たとえ自分の所得が支給範囲内であっても、同居することで児童扶養手当の対象外となります。
自分の所得の変動がなければ、まず両親の所得額から確認してみてください。
Q2: 実家の両親の所得がわかりません。どうすればいいですか?
A2: 確定申告や源泉徴収票で確認ができます。
年金をすでにもらっている両親であれば、毎年2月3月ごろに必ず確定申告をします。手元に控えがあるはずなので確認してみましょう。
源泉徴収票は年末頃に職場からもらえます。
Q3: 同居した場合、母親の所得は影響しますか?
A3: 所得により影響がでる場合があります。
父親の扶養に入っている場合は問題ありませんし、母親の所得が影響することはありません。
Q4: 同居していることを申告していません。そういった場合どうなりますか?
A4:すぐにお住まいの福祉事務所に申告してください。
誤った申告状況で児童扶養手当を受給している場合は不正受給となります。
家族構成が変更した場合、両親と同居した場合、何かしらの変更が生じた場合はなどは速やかに申告してください。
Q5: 児童扶養手当がもらえるかどうかはどこに行けばわかりますか?
A5:お住まいの福祉事務所で確認してもらえます。
児童扶養手当がもらえるかどうかの確認してもらえますので、不安な方は事前に相談してください。
場合によっては両親の所得確認をしてもらえます。
まとめ
児童扶養手当は実家暮らしでも受給は可能です。
ただし、チェックすることは次の通りです。
- 同居する人(両親、兄弟等)に高額所得者がいないか。
- 高額な養育費をもらってないか。
実家暮らしをする場合は、同居する父親もしくは母親の所得額を必ず確認してください。
自分にはそれほど収入がなくても、同居する両親が高額な所得があると児童扶養手当は支給対象外となります。
同居するか別居するかで児童扶養手当額にどれだけ影響してくるかを事前に確認しておくと安心ですよね。
それでも自分ではなんだかよく分からない場合は、お住まいの福祉事務所に相談に行けば教えてくれます。
私も最初相談に行く時は不安でしたが、窓口の方が事細かに教えてくれてとても安心しました。
ぜひ足を運んでみてください。
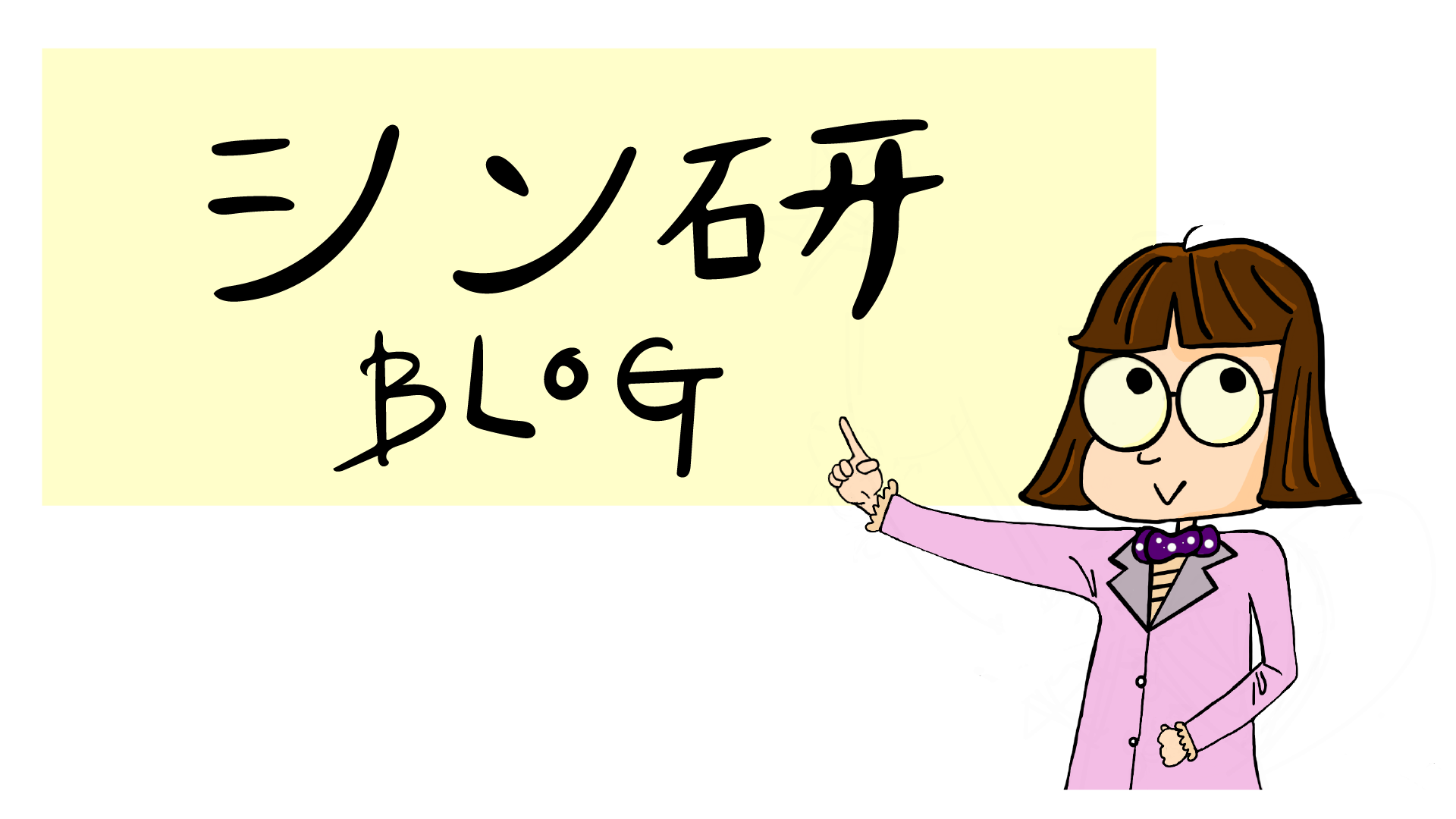

コメント